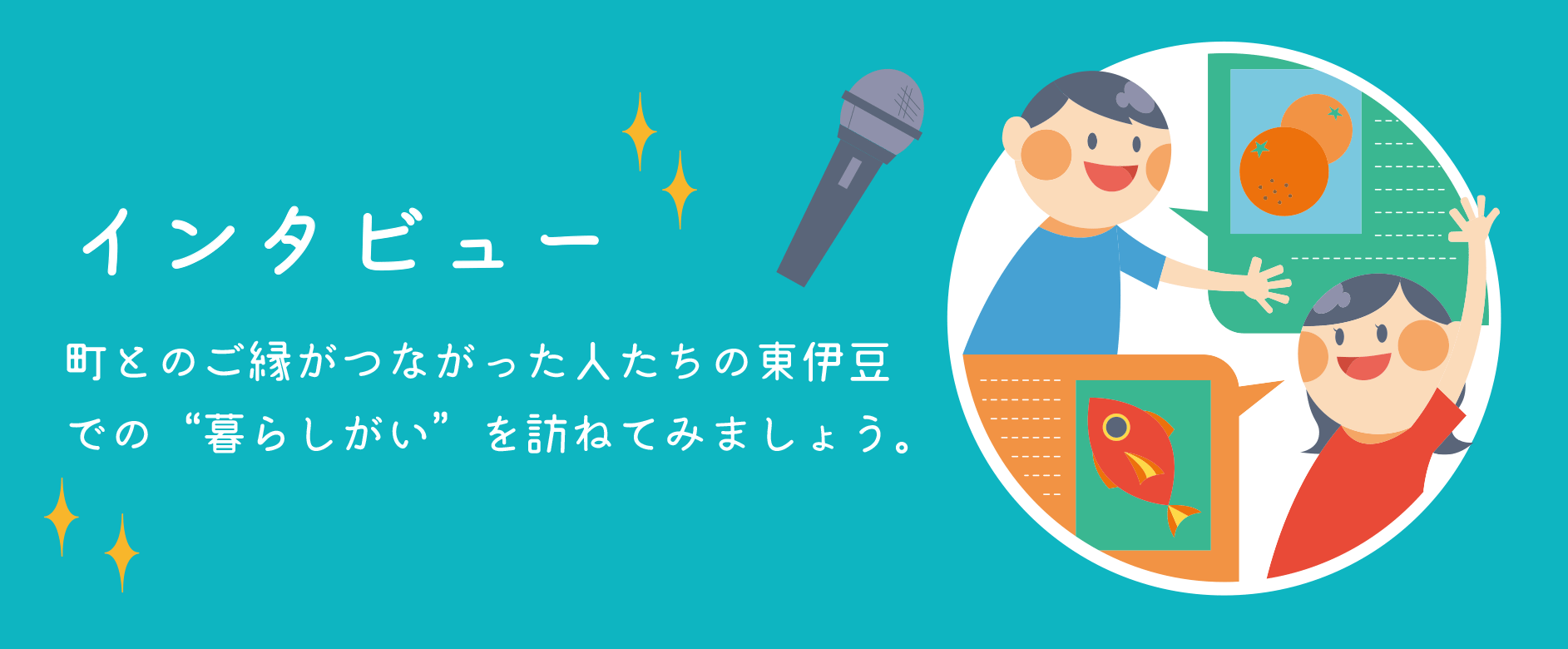住む

東伊豆町民インタビュー NO.80 梅田留奈さん前編

今回は東伊豆町地域おこし協力隊の梅田さんにインタビュー。
梅田さんは学生時代から東伊豆に関わりを持ってくれていて、この東伊豆通信のデザインも担当してくださっています。
まさか取材させてもらう日が来るとは…感慨深いです。
そんな梅田さんですが、まずどのように東伊豆と関わりを持ったか、協力隊になるまでの経緯を教えていただきたいです!
よろしくお願いします。
私は北海道出身で、デザインを勉強したいと思い、国公立大学の静岡大学を受験しました。
入学したのは静岡大学の地域創造学環という静岡県内各所の地方と呼ばれるような地域課題が山積しているような場所に定期的に通うフィールドワークという授業が必修科目になる専攻でした。
私はデザインを学ぶことが最優先だったため、地域のことはさほど興味はなかったんですが、気がついたら東伊豆町民になっていましたね…(笑)
そのフィールドワークに東伊豆町の枠が私たちの代から追加されたためそこを希望し、希望者多数の激戦区の中、なんとか東伊豆町に通うことが決まりました。
静大のフィールドワークは年に6回大学指定のフィールドに通うという必修科目で、わたしたちは荒武さんたちに受け入れてもらう形で、2017−2019年にお世話になりました。
大学を卒業してからも、デザインの仕事で町と関わりを持ちながら定期的に通いつつ東京の広告代理店に勤めていたんですが、東伊豆で稲取駅のプロジェクトができることを知って、地域おこし協力隊になることを決めました。
協力隊になるという報告を大学の担当教員にしたとき「梅田が一番地域で活動することに興味なさそうだったんだけどな」と驚かれました(笑)



たしかに、一番興味なさそうだった!
そんな梅田さんが学生時代この町を最初に訪れたときに感じた第一印象ってどんなものでしたか?
訪れてまず思ったのが、若い人がいないなあという印象です。
ただ、町歩きをしていると、どこからきたのか?と声をかけてくれる気さくなおばあちゃんがいたことも印象に残っています。
そのあとも、軒先の干し柿をおすそ分けしてくれる方と出会ったりして、自分たちのようなよそ者とコミュニケーションを気軽に取ってくれる人が住んでいる町があるんだ。と、発見というか驚きがありました!


なるほど、訪れて最初にこの町の人の温かさに触れたわけですね。
定期的に通ったフィールドワークではどんな活動が印象深く残っていますか?
私の中では2019年3月に開催された雛フェスが印象深いです。
その際、地元のみなさんに参加してもらいながら完成させるライブペイントを実施しました。
このとき初めて大学時代学んできた「アートやデザイン」と「地域」の掛け算を実践の場として実現できたという手応えがあったんです。
私が所属していた静岡大学地域創造学環境のアート&マネジメントコースは、アートを使って 地域を活性化するっていう目的があるはあるけど、実際アートでどう地域を活性化できるのかって、あんまりイメージが正直湧いてなくって。
このライブペイントを経て、こういう風にしたらアートって地域に人を呼び込めるんだなとか、盛り上げられるんだなみたいなことが初めてわかったというか、実感できて、地域でそういうことするの面白いなって、意識が変わったんですよね。
移住した今、雛フェスを主催した商工会の人たちとお会いして当時の話をすると感慨深く思います。



実践の場としての東伊豆に価値を見出してくれたんですね。
素敵な体験をしていただけてよかったです!
デザインを実践する場としての東伊豆について、もう少し詳しくエピソードを教えてもらってもよろしいでしょうか?
それまでの私はデザインを授業などで作ることはあれど、誰かの手に渡るものを制作したことはほとんどなくて…東伊豆で人の手に渡る媒体を作らせてもらえたのはいい経験でした。
座学とのギャップがあって、実在するイベントのチラシデザインについては、そのデザインを手に取ってくれるターゲットをちゃんと考えないといけないんだなということを実感しました。
雛フェスでは子どもむけに抽選券をデザインしたのですが、子どもを対象にしたデザインは授業ではやらなかったので、デザインについて運営側からの修正が多かったんです。
そこで、受け取ってもらい見てもらうためのデザインが大切なんだなということに気がつけたということがありました。
東伊豆って活躍のフィールドを求めている人がチャレンジをするのに最適な町だなと。
例えば私が東京で会社をやめて東京でデザイン会社を起業するとして、実態としてのアウトプットができるような機会にはなかなか恵まれていなかったと思います。
駅のプロジェクトに携わることができるチャンスなんてそうそう巡ってくるものでもないですし、チャレンジの場をたくさん創出するこの町の文化を次の世代にも引き継いでもらえたらいいですよね。


なるほど、チャレンジするのに最適な町。しっくり来ますね。
梅田さんの進まれている道って、生き方として特殊な進路なのでは?と思うんですが、東伊豆でのフィールドワークの時間が影響していたりするんでしょうか?
そうですね。学生時代、東伊豆に通っていたメンバーからの影響が大きかったと思います。
私を含めて同級生は4人で東伊豆町にフィールドワークに通っていたんですが、他の3人がいい意味でぶっ飛んでいて、1つ1つの行動に驚かされ、刺激をもらえる関係性なんです。
働き方含めて生き方も私にはない選択をしていて、3人の転職や離職の変遷を見ていなかったら、協力隊に転職しようとはならなかったかもしれません。
周りが会社に入社してからずっとそこに在籍しているような人たちだったら、多分私はこの選択を取ってたなかったなと思ってて。
1番身近で長い時間を共にした同期が、結構変わったキャリアの積み方をしたから、私も心配なく協力隊の道を選択できました。
しかも絶対この人たちは応援してくれるってわかってるんで、この街に来れたって感じですね。
なので一番刺激をもらえるし絶対味方でいてくれる仲という間柄です。
後輩にも恵まれました。


いい仲間に恵まれたんですね!
僕もそうですけど、東伊豆に関わる人は人生をダイナミックに変える行動力がある人が多い気がしますね。
そこのところ梅田さんはどのように感じますか?
町自体がそういう人を呼び込んでいるというのもあるだろうし、私の場合は荒武さんたちと一緒にフィールドワークで活動していたからというのはあると思います。
他にも学生時代に転職だったり起業をして、東伊豆町に移住してきた人と関わり合いを持つことができたため、その影響も大きいと思います。
そういう大人たちと出会って、今の環境が自分に合わなかったら仕事も住む土地も変えていいんだな、という意識が育ったんではないかなと。
町のなかで多様な生き方をしている人と会うことができたんですけど、学生の時から生き方は自由に選択できるという価値観に触れていたからこそ地域おこし協力隊という仕事が選択肢になったんだと思います。
本当に協力隊として町に来れてよかったと思う場面が多くて、学生時代に東伊豆をフィールドとして選んでいなかったらありえない道でしたね。


周囲の環境は大いに影響してきますよね。学生時代の柔軟な時期に色々な価値観に触れていると選択肢が増えるのかもしれません。
前編では梅田さんが地域おこし協力隊になるに至った源流を追わせていただきました。
後編ではお仕事のことも含めてより詳細にお話を伺っていけたらと思います!