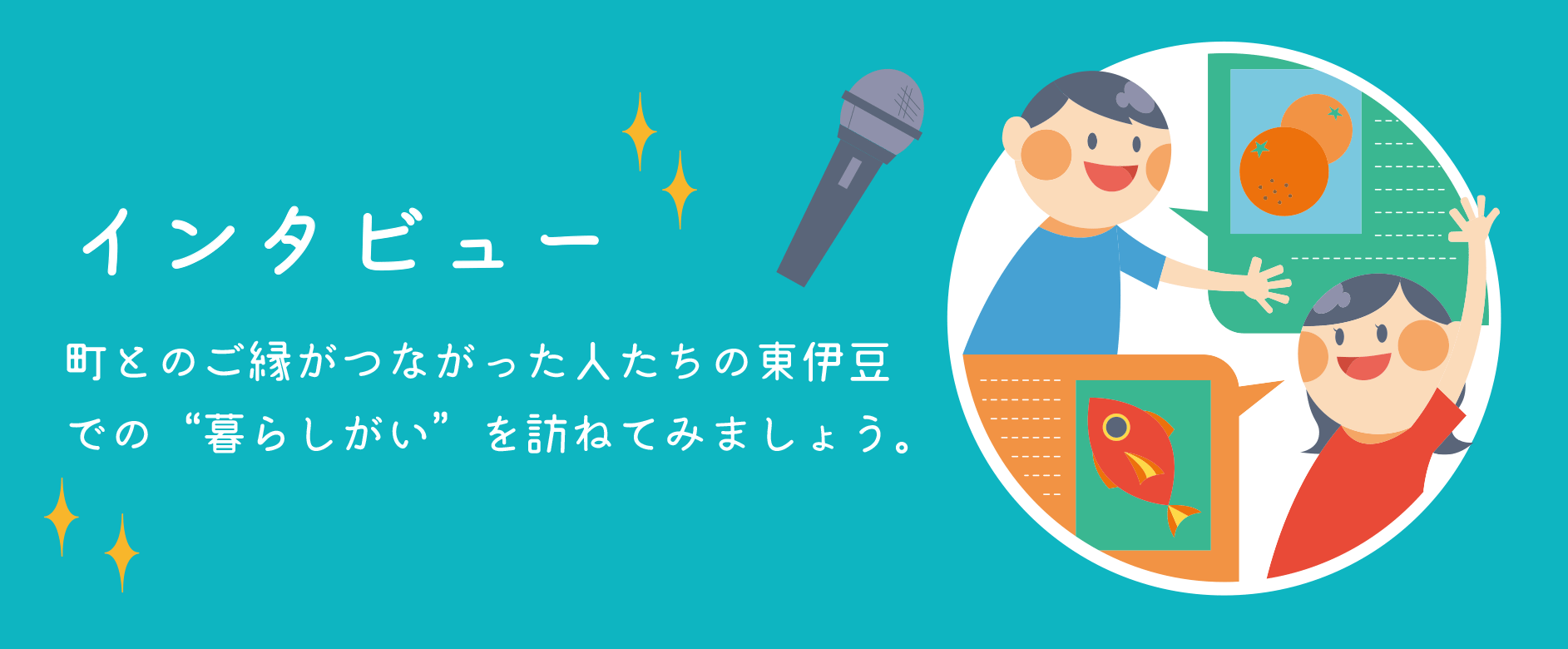住む

東伊豆町民インタビュー NO.81 井上憲作さん、井上典子さん前編

本日は井上さんご夫妻にインタビュー。
井上さんたちは移住したてのご夫婦です。
東伊豆のどんなところに魅力を感じたのか、新規事業としてお総菜やとゲストハウスを始めるに至った経緯など伺っていけたらと思います。
最初は東伊豆町への移住の動機とその背景についてお教えいただきたいです!
一番最初のきっかけはスキューバダイビングです。
西伊豆や南伊豆をメインにダイビングしていました。
ベストなタイミングで海へ潜るためにはこの土地にいる必要があるんですが、当時は東京に暮らしていました。
ダイビング仲間との会話の中で空き家を改修して拠点にしてみたらいいのでは?という話になってそういうのはありだねってなんとなくの話は随分前からしていたんですよね。
通っていた西伊豆のダイビングショップは10年くらい併設の宿泊施設をやっていて、地元に馴染むのに苦労している様子を目にして、地域に入ることについてのハードルを感じるのと同時に、地方に移り住むのはリスクなのかもなと感じていました。
ただ、伊豆への移住の可能性を捨てきれずに過ごしていて、ある時元同僚に相談があると話を持ちかけられ会うことに。
その相談とは別の会話の流れで稲取訪問の話題が上がりなんとなくその旅に付いていくことになりました。
西伊豆のダイビングショップの苦労話を聞いていたから、そこまで期待はしていなかったんですが、東伊豆を訪ねてみると地域外の人間が関わりを持つ下地があることがわかりました!

私も西伊豆にはダイビングで通っていて、駅はないけど、温泉地もあって、東伊豆ほどは観光開発されていない自然がより豊かな印象を持っています。
稲取から帰ってきた夫は、東伊豆で暮らすことについてすごく盛り上がっていて、彼の本気度が伝わってきました。
家にあるホワイトボードでなにやら今後のスケジュールを書き出していましたね。

ホワイトボードを使って何ができそうか、検討を深めていきました。
いつでも見える場所にそのホワイトボードがあるので、いつでも伊豆への移住のことを考えていたんです。
妻にも紹介したく、現地に赴いて暮らしのイメージを膨らませてもらおうとすぐに動きました。



井上さんにとって移り住むのにイメージにぴったりな町だったんですね!
伊豆への暮らしのイメージは、どんな背景から出来上がってきたんでしょうか?

私の中で一番大きいのが、20年くらい携わっている今のマーケティングの仕事を続けていくイメージを持つことができなかったことです。
資料を作って、プレゼンして、手に取れない仮想空間での仕事という感覚があって、20年間やってきたこの仕事を、これからも続けていくというイメージが湧かなくなってしまったんですよね。
年齢的にも時代的にも今までと同じ仕事を続けられるのかの不安もありました。
そこで、新天地を求めるとしたら手に触れられるものを売り買いしたり、自分たちで運営していくという、これまでの誰かの事業サポートではない、自分自身の実態のある事業をサービス化していきたいという思いを持つようになったわけです。
助け合いと支え合いのバランスも加味しながら、自分が将来年を取ったら困る領域を先回りしてサービス提供できるといいなと考えていて、高齢社会においては買い物難民が増えるので米、洗剤、牛乳のような重いものやトイレットペーパーなどかさばるものは特に御用聞きのようなサービスが必要になってくるのではないかなと考えています。
出身は茨城県のつくば市で、中学からは東京に引っ越して暮らしていました。
つくばには実家はあるけど帰りたいともそこまで思わないし、東京にもそこまで愛着はないんですよね。
故郷という故郷が思い至らない。故郷と呼べるどこかを探していたのかもしれないです。
東京にみんなが求めるようなキラキラをそんなに感じないですし。

故郷と呼べる土地を求めていたというのは、首都圏での暮らしが長い井上さんならではの感覚なんでしょうね。
典子さんは移り住むことに対してどのようなイメージを描いていましたか?

私は東京生まれ東京育ちですが、東京への愛着は夫と同じでさほどないんです。
料理だったらイメージが湧くけど、移り住んでからの暮らしについてのことは思い描くことはできなかったです。
ただ、伊豆自体は好きだったので、移り住むということ自体にハードルを感じませんでした。
住まいを東伊豆に構えてからも車がないときは徒歩で生活していたけれど、不便さもそこまで感じなかったかな。
東伊豆、特に稲取って、生活する上での機能が整っているので不便さはそんなにないんですよね。
ただ、夜ご飯を食べに行くのに困ることはしばしばありましたね。

そうそう、今も東京都二拠点の生活を送っているんですが、まだ生活の比重が東京に多かったとき、この町での食事に困りました。
私は料理をしないので、どうしても外食やコンビニ弁当になってしまう。
昼間食べに行くとすると1,000円以上かかるお店が多いため、この生活を続けるのは難しいなと感じていました。それが東伊豆町の生活における最初のイメージです。


なるほど、町の食事事情に関して課題感をお持ちだったんですね。
それが、「和ぎ」というお店でお二人がお総菜やとゲストハウスをやろうと思い至ったきかけだったのでしょうか?

その課題意識もありましたし、きっかけは知人の「お総菜屋さんがいいですよ」という一言でした。
本人は何の意図もなく話していたと思うんですが、自分だけで動いていくスピード感よりも、周りの意見も取り入れながら決めていく方が近道にもなるという考えのもと東伊豆での仕事を選定していきました。
あと妻は以前喫茶店を友人と二人で営んでいた経験があって、その時やっていたランチは概ね評判がよかったんです。
当時ダイビング仲間を招いてパーティを開くこともしていたんですがその時も好評でした。
東伊豆町に移り住んで、私のように食事に困るという人は少なからずいるだろうなという見込みがあったため、妻の料理は僕たちのこれからの仕事において、ストロングポイントとなるなと考えたんです。

喫茶店は高校時代の友達とかっぱ橋で20年ぶりに再会したことがきっかけでした。
その友人が純喫茶を開業するというのでそれを手伝うことになり、お店に来てくれたお客さんの中に夫がいたんです。
調理師の免許もその時に取得しました。


また、少子高齢化で人口減少が顕著な現代社会において、コンパクトシティという考えはとても適していると思っています。
しかし、それを回答として示せている場所がどこにもないんじゃないかという考えを持っていて、民間として稲取・東伊豆という単位で暮らしやすいサービスを提供していけたらいいなというところが私達の仕事を作っていく背景にはあります。
これから開業予定の物件なら、お総菜だけでなく、移住でも観光でもない、継続的に地域に対して多様に関わる人が中・長期滞在できるゲストハウスも作れるのではないかということにも思い至りました。
地域の中に選択肢を増やしていくことが豊かな生活につながる。
そういう選択肢を持てる町になっていくといいですよね。

選択肢が多様な町が出来上がると、今よりも多様な背景を持った人の出入りが予想できて、もっと面白いことが起こる町になりそうですね!
井上さんご夫妻のお店「和ぎ」ができる日が楽しみです!
引き続き、後編でもよろしくお願いいたします!